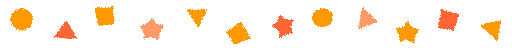
| <東京都への要望書(2007年)の紹介> 要望書  2007年7月  全国視覚障害児(者)親の会東京支部 全国視覚障害児(者)親の会東京支部昨年4月より施行された障害者自立支援法は、障害者の現在とこれからの将来にとって憂うべき事態であると痛感しています。 私たち視覚障害児(者)の親は、視覚に障害をもった子供たちがすこやかに社会生活をおくっていくことができるように、学齢期や卒業後の社会参加のなかで、その持てる力がのばされ、成長していくことを望んでいます。 そうした中で、社会での障害者施策は様々にすすめられつつありますが、実際のところ視覚障害者にかかわるものがまだ限られています。私たちは障害者施策をよりつよめてもらうとともに、それが視覚障害者に十分な配慮されたものであることを切に望んでおります。 ところが、昨年4月より施行された障害者自立支援法は、通所や入所等の障害者施策を利用している全ての障害者に毎月数万円の新たな負担を課しており、この間行われた障害程度区分認定で、現在利用している施設を利用できなくなる事態も生まれかねない状況もあり、現在到達している障害者施策と障害者の生活が根底からゆらぎかねない事態となっています。現在の障害者施策を利用している障害者にとっての利用が制限され、また後退させられるようなことがあってはいけません。 障害者、そして視覚障害者の現在と将来のために東京都に次のことを要望いたします。 福祉保健局関係 1.障害者自立支援法への移行措置の見なし期間で、この間の障害程度区分認定による区分で、現在利用している施設の通所者・入所者が、利用できなくなって退所することのないようにしてください。都としてそのための具体的な措置をとってください。 2.現在の障害程度区分認定は、障害者の現状を反映させたものとはなっていません。現在の介護保険の要介護認定調査項目をベースにした認定では、障害者の現状を反映できません。障害者の現状を反映したものにかえてください。特に視覚障害については、1項目「視力について」とあるだけで、視覚障害に係わる生活全般への影響、実際の困難が明確には反映されていません。視覚障害に係わる現状が反映するものにかえてください。そのために都として、国にあらためて働きかけてください。 3.障害者自立支援法の施行にともない、障害者本人の負担が激増しています。施設の通所者・入所者は月に数万円の新たな負担増となっているなかで、来年度までの「特別対策」だけでは、負担増の激変はおさまりません。施設利用負担金の助成については、現在各区市町村において一部助成している所もありますが、都としてのも助成し新たな軽減措置をとってください。 また、国にたいして、障害が重く多くの障害者施策を受けている障害者の負担が重くなり、障害者の自立からかけ離れてしまう「応益負担」をおこなわないように働きかけてください。 4.障害者自立支援法の施行後、事業者が通所施設等での運営においてうけとる費用が、日払い方式になっており、利用者の通院や本人の状況等での通所減はおこるものであることから、運営が困難になっています。都として日払い方式で減額された分について「減収の著しい事業者」だけでなく、減額で困難な事業者すべてに助成してください。 事業者の運営が不安定になると、障害者への理解のある専門性をもった職員が安定して集まらず、利用者への不安定なサービスの提供となってしまいます。ぜひ支援してください。 5.移動支援で、学校の送迎でも利用できるように区市町村に働きかけてください。 6.負担の基準となる収入は本人のものに限ってください。自立ではなく家族への依存になる世帯単位の所得の算出おこなわないように、あらためて、国に要望してください。 7.都のおこなっている心身障害者の医療費の助成制度を維持し、現行の障害者本人に負担がなく医療にかかれる制度を堅持してください。 8.点字使用の視覚障害者がガイドヘルパー等の諸制度をつかう場合、点字の契約書および点字の実績記録票を準備させてください。都が指定している指定事業者にこのことを義務づけてください。 9.ショートステイ(短期入所)の利用できる場所をふやしてください。利用年齢を18才以上としている区市町村へ低年齢でも利用できるように働きかけてください。 10.特別養護老人ホームでのマッサージ師雇用のための補助金をひきつづきカットしないでください。 11.福祉のまちづくり条例にもだされているような視覚障害者への点字誘導ブロックへの理解啓発をはじめとする視覚障害者へのマナーの喚起や広報、白杖への理解啓発、盲学校周辺での所在の広報などをつよめてください。区市町村に視覚障害者に関する理解啓発をおこなうように、ひきつづき働きかけてください。  教育庁関係 1.特別支援学校になっても「盲学校」の名前は残してください。特別支援学校において、視覚障害教育の専門性を確保できる措置を具体的にとってください。感覚障害としての視覚障害者への教育にふさわしく、その特質と専門性をいかした学校運営をすすめてください。とくに盲学校と他障害種別を併せた特別支援学校においては、必ず視覚障害部門を設置し、専門性の確保と適切な学習環境の保障をしてください。都の特別支援教育の中での視覚障害教育と盲学校のあり方をしめしてください。 2.視覚障害者への教育をすすめる上で盲学校のセンター的役割がもとめられており、コーディネーターや地域への支援・援助に係わる要員が必要であり、現在の定員内では在校児童生徒の学習や訓練に支障をきたします。特別支援教育コーディネーターの複数専任配置をおこなってください。現在、盲学校にコーディネーターが何名配置されているか、専任・兼任に分けて各盲学校別に教えてください。 3.視覚障害者にとって通学を保障し、生活経験、社会性をまなぶ大事な教育の場としての寄宿舎については、感覚障害としての視覚障害教育の特性をしっかりとふまえ、現在の寄宿舎は存続させ、統廃合等はおこなわないでください。都の計画とその進捗の状況を教えてください。 4.視覚障害者が社会参加していくに必要な力をつけるため、重複障害者も学べる生活科、職業訓練科を高等部に設置してください。神奈川県が認可した重複障害者の教育ニーズに応える高等部専攻科生活科を東京都でも設置してください。 5.視覚障害教育の専門性の向上をはかるため、視覚障害教育にかかわる研修をすすめてください。盲学校免許保有者を配置し、盲学校の勤務教員全員を取得させてください。各盲学校ごとの取得状況を教えてください。要望のある必要な場に言語聴覚訓練士を配置してください。 6.盲学校の休業中に、卒業生も参加し利用できる企画などを充実させてください。その情報を知らせてください。   |
「東京都への要請(2006年)の紹介」ページへもどる
「東京都への要請(2005年)の紹介」ページへもどる
 トップページへもどる
トップページへもどる